初めての電車・電車の乗り方
青春18きっぷ以前に「普段は車ばかりで電車に乗る機会がない」という方向けに基本的な電車の乗り方を述べています。制作者の都合上、最寄り駅の尼崎駅から、最も近い大きな駅である大阪駅まで乗るものとして説明しています。
基本的な流れは「きっぷを買う→改札口を通る(入場)→電車に乗る→降りる→改札口を通る(出場)」となります。
きっぷ(切符)を買う
改札口を通る
ホームへ移動
電車を待つ
電車に乗る
降車駅に着いたら
その他
席を譲る
本項では「切符」「きっぷ」=「乗車券」を指します。
まずはきっぷ(乗車券)を買う
多くの駅では、駅の中にきっぷ売場があります。「きっぷうりば」との案内表示もあります。ほとんどの場合、自動券売機で買うことになりますが、自動券売機の上方に運賃表(その駅を中心とした路線図と、各駅までの運賃が書かれている)があり、降車駅(降りる駅)までの運賃を確かめてからきっぷを買うことになります。
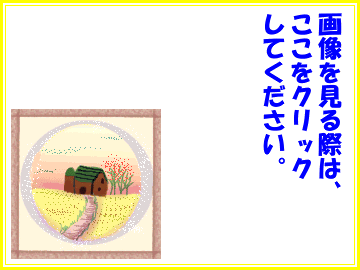
運賃を調べる
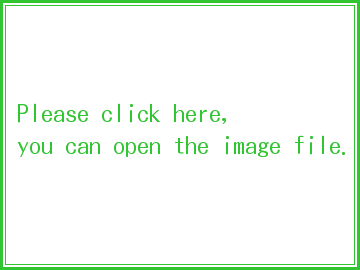
自動券売機上の運賃表(下画像・以下は「運賃表」と書きます)を見て、降車駅(電車を降りる駅、移動を終える駅)までの運賃を確認してください。
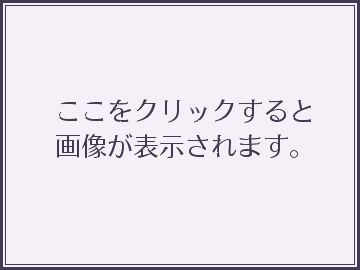
で、大阪駅までの運賃がいくらか探してみましょう。運賃表を見ると、180円であることがわかります。なお、子ども(小学生)は半額(10円未満は切り捨て※)です。
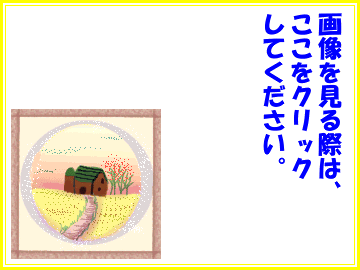
※ JR以外はほとんど「切り上げ」です。
自動券売機で切符(乗車券)を買う
最近の券売機は、お金を入れる前に「何をするか」を画面から選ばなければならないようです。(※) 以下では、大人1人分の切符を買うものとして説明しています。
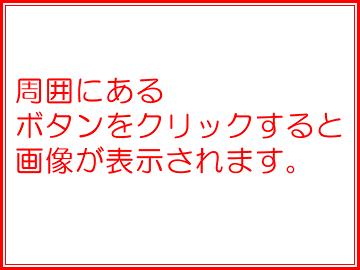
はじめに「きっぷを買う」を選びます。タッチパネルですので、その部分に触れてください。反応が悪い(画面が切り替わらない)場合は、その周辺を何度も触ってみてください。
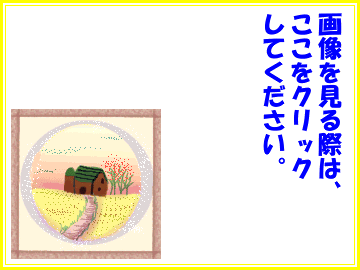
ご注意 黄枠の部分に記載されている運賃は2014年3月以前のものです。現在の尼崎駅から大阪駅までの運賃は180円です。(切符参照)
運賃が書かれた画面になるので、170円の部分(赤で囲った部分)を触ってください。すると画面が変わります。
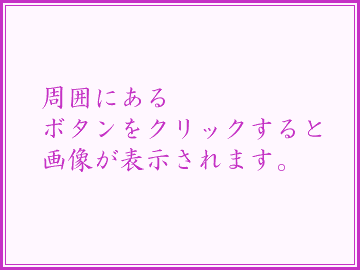
この画面でお金を入れる場所(「1台をアップで・説明つき」を参照)からお金を入れてください。
で、運賃分の金額が入った時点で、「お金を入れる場所」の下から切符が出てきます。お釣りも出てきます。
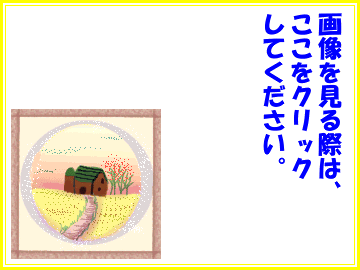
切符とお釣りは取り忘れないで下さい。
余談:つり銭が90円あることに疑問を抱く方もいるかもしれませんが、160円入れた時点で10円玉が無いのに気付き、仕方なく100円玉を入れたことが原因です。
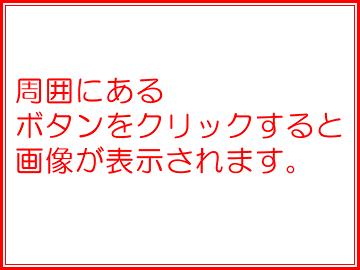
あまりないと思いますが、運賃表にない駅まで行く場合は、基本的に「みどりの窓口」で買うことになります。駅によっては、「みどりの券売機」といった名称の券売機でも買えますが、初めての場合は窓口で買う方が無難です。
※補足
タッチパネルの「きっぷを買う」を押さずにお金を入れると、運賃が書かれた画面になるようです。
改札口を通る
改札口から向うは、切符を持ってない人は入れません。列車に乗らない人も入場券が必要になります。
最近は自動改札機が多いです。切符の裏側が黒か茶の場合は、自動改札機を通ります。(ただし、青春18きっぷは自動改札機を通りません。)
矢印(←)の書かれた通路を通ります。入口側(手前)のゲートが開いているのがわかるでしょう。逆に、通れない通路(進入禁止のマーク)は、入口側のゲートが閉じているのも下画像でわかると思います。
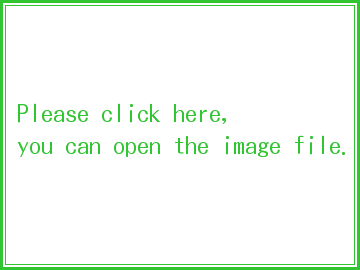
※ ICカード専用の通路もあります。この場合、紙の乗車券を持った人は通れません。
※ どこを通れるかの表示方法は、鉄道会社によって異なります。
実際に自動改札を通りましょう。所定の場所に先ほど買った切符を投入します。
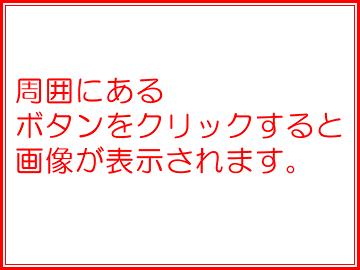
瞬時に前方右側に切符が出て来ますので、切符を取って先に進みます。
駅によっては一方通行でなく両通の場合があります。その場合は、反対側から切符を入れられると、手前のゲートが閉まり通行不可になります。自分が通ろうとする直前にこれをされると、かなりムカつきます。
ホームへ移動
多くの駅では、改札口の向うに発車案内板や行先案内板があります。これを見て、目的地への列車がどのホームから発車するか確かめ、そのホームへ行きましょう。
尼崎駅の場合は、4方向(大阪方面、北新地方面、神戸方面、宝塚方面)に電車が発車しますので、4種類の発車案内があります。
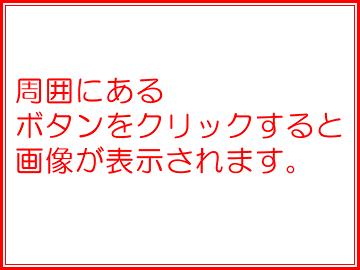
尼崎駅から大阪駅へ行く場合、5〜8番乗り場の列車に乗ればいいのですが、新快速が発車する8番乗り場以外の5〜7番乗り場から発車する電車すべてが大阪駅を通るとは限りません。(JR東西線・北新地方面の電車も発車します。)
私自身は習慣的に5・6番乗り場に行くことが多いのですが、日中に大阪駅に行くのであれば、本数はやや少ないのですが7・8番乗り場の方が確実です。7・8番乗り場からの列車(京都方面)は、日中はすべて大阪駅を通り、尼崎を出ると次は大阪です。ただし、混雑していることが多いです。7番乗り場からは福知山線からの特急(乗車券以外に特急券が必要。大阪駅は通る)も発車するのでご注意を。
電車を待つ
ホームに着いたら、さらに発車案内板があります。改札口のものとは違い、乗車位置が書かれています。(乗車位置については、地方によっては書かれていないこともあるし、表記方法が異なることもあります。)
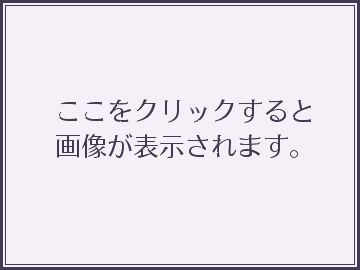
赤枠の電車に乗ります。乗車位置の欄に「白○1〜7」と書かれていますが、足元を見ると、○や△などの記号と番号が書かれています。そこが乗車位置です。
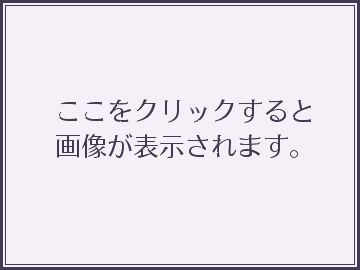
ここで問題です。この場合は、どこで待っていればいいでしょうか?
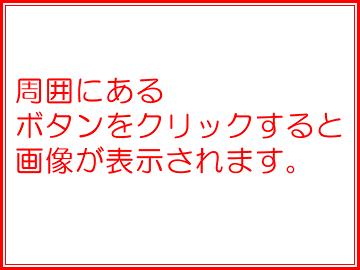
この場合は、「白○の1から7までのどこかで待てばいい」ことになりますので、上図では「白○の6」が正解です。発車が近付くと、待っている人がすでにいるはずです。
なお、白○の3は「女性専用車」です。該当する方は避けましょう。また、優先座席に近い乗車口には、その旨表示があります。
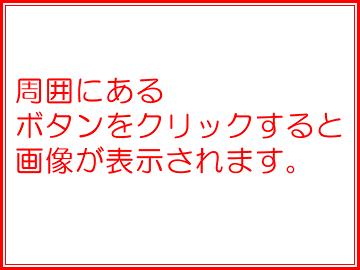
電車に乗る
電車が到着しても・・・
電車が到着しドアが開いても、すぐに乗ってはいけません。
まずはドアの両側どちらかに立ち(誰かの後ろに並んでいる場合は、その人の後にいる)、降りる人を先に通します。降りる人が終わった後、前の人から順番に乗ることになります。
下の動画は上から撮影したものでドアは映っていませんが、乗ろうとする人がドアの両側に立ち、降りる人がその間を通っていく様子がわかると思います。(再生時間は1分6秒・無音)
右をクリックし再生ボタンを押してください → 動画を見る
電車の中では
車内には座席があります。座っている人がいなければ、座ってもかまいません。座席には大きく分けてロング・クロス・ボックスの3種類があります。クロスやボックスタイプがメインでも、車両中の一部の座席がロングシートの場合もあります。
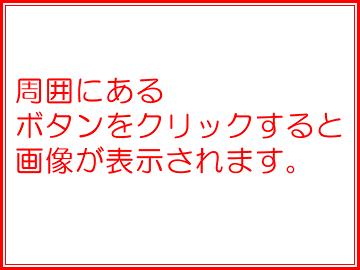
降車駅まで電車の中で過ごすことになりますが、周囲の人に不快に感じられないよう配慮してください。例えば、
- 騒がない、大声で話さない(携帯電話での通話も含む)
- ヘッドホンの音漏れ
などです。また座っている時に、お年寄りや体の不自由な人などが現れた場合は、席を譲りましょう。(詳しくは右側メニューの「その他」をクリックし、一番最後の項目をご覧ください。)
車内では、次の停車駅などが案内されます。降りる駅が近付けば、降りる準備しましょう。また、車両によっては、車内の表示板に次の停車駅が表示されるので参考になると思います。
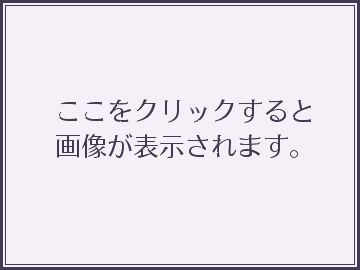
降車駅に着いたら
降りる駅に着けば、電車を降ります。で、近くの階段やエスカレーターで(又は目的地に近い階段など)から出ます。通路を通ると改札口があります。
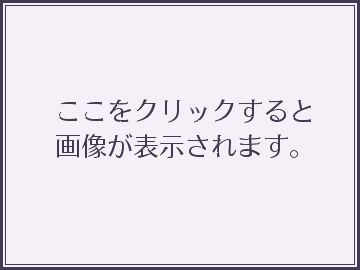
再び改札口を通ります。乗車時と同じように所定の場所に切符を入れますが、今度は切符は出てきません。(※) そのまま通ってください。
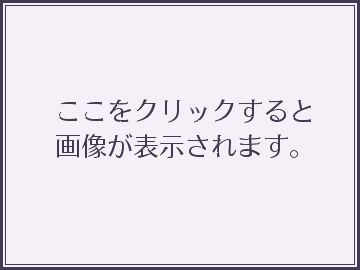
これでおしまいです。文字にするとごちゃごちゃしますが、難しいことではありませんので、ぜひやってみてください。
※ 運賃が不足している場合(券面に書かれた運賃よりも、実際の運賃が高い場合)は切符が出て来てピーポピーポ音が鳴り、ゲートが閉まって通れなくなります。(恥ずかしいです。) この場合は、乗り越し精算機(たいてい近くにある)で不足分の運賃を払うと「精算標」がもらえるので、それを自動改札気に入れて自動改札を通ることができます。又は、有人の改札口の係員に切符を見せ、差額を払うことで出ることができます。
その他
乗り換える場合
同じ鉄道会社の場合(大阪駅から環状線に乗る場合など)は、多くの場合、通路を通って該当するホームへ行き、そのホームから発車する電車に乗ります。
異なる鉄道会社の場合(地下鉄や阪急電車、阪神電車)は、改札口を出て、その鉄道会社の駅に行って、再度切符を買うことになります。
ICカード(ICOCAなど)を使う
あらかじめチャージしておくことで、きっぷを買わずに電車に乗ることができます。この場合、自動改札口の所定の場所にICカードをタッチすることで改札口を通ることができます。が、電車に乗る機会の少ない方の場合は、無理に使うこともないと思います。
いらんことですが、私の場合は、回数券(金券ショップでのばら売りを含む)を利用することが多いので、最近はあまり使っていません。
席を譲る
いろいろ言われていますが、実際に席を譲るとなると勇気もいるし、断られると気を悪くすることもあると思います。経験上、うまく行きそうな相手や座席位置をご紹介します。
お年寄り
スーツ姿(身なりの良い)の人、リュックサックを背負っている人は断られる可能性が高いです。(元気な人が多いので)
一方で、スーパーの買い物袋や処方薬(病院に行った帰り)を持った人、腰が曲がっている人は体力的に厳しい人が多いので、譲ると喜んで座ってくれると思います。ただし、座席位置(後述)も考えて下さい。
体の不自由な方
杖を突いて歩いている方(年代関係なく。白い杖以外)は成功率が高いです。
白い杖を持っているのは目が不自由な方ですが、そういう方は自分が意図しないことをされると大変なことになりますので、声を掛けないほうが無難です。どうしてもというなら、座らせた後に「右(左)側にドアがあります」と言うか、その人が降りる駅まで乗車し、降りるまで案内するなどした方がいいでしょう。
妊婦・小さな子供を連れている方
変に気を使うことはありませんが、立っているのが辛そうだったら譲ってあげるといいと思います。
座ってくれそうな場所、座席タイプについて
優先座席はもちろんですが、ドア(出口)の近くの席がおすすめです。
座席タイプでは、ロングシート(多くの通勤車両)の方がおすすめです。(座席タイプの例は上述)
その他
譲ろうと思っても、話しかけるのが負担でしたら、それらしき人が来た時に黙って立ち去るのが無難です。
質問検索
当ページを開いた際の「質問めいた検索語」について、その答えを述べています。
行先の手前(途中駅)で降りることはできるか?
※「降りる」「下車」=「電車を降りて、改札口を出る」と仮定して説明します。
右では「尼崎駅から大阪駅まで」を例に説明していますが、当ページに載せている「尼崎駅から180円区間の乗車券」で、大阪駅の手前にある塚本駅(運賃は160円)で降りることもできます。
ただし、塚本駅出口の自動改札機に切符を投入すると、切符は無効となり回収されてしまいます。(その後、大阪駅には行けません)乗車券に「下車前途無効」と書かれているのはそういう意味です。
100km以上の区間を移動する場合は、紙のきっぷを購入することで、一定の条件の下で途中駅で下車しても、目的地までその切符を使用できる場合があります。(「途中下車」といいます。)
電車の切符は電車内で買うと高い?
乗車する区間が同じならば、駅で買おうと、車内で買おうと運賃は同じです。
が、大阪や東京など都市部の場合、車内で切符を買うことはほとんどありません。
自動改札で乗車券を取り忘れた
自動改札を通った直後に気付いた場合は、自動改札機に切符が残っているはずなので、戻って確かめてみましょう。
切符を取り忘れた場合は、自動改札機が警報音を出し、一時的に通行不可になるはずです。(他の人に切符を取られる可能性は低いです)
時間がたってから気付いた場合(ホーム上や電車に乗ってから)は、降りる駅の駅員さんや乗っている列車の車掌さんに言って、指示に従ってください。
